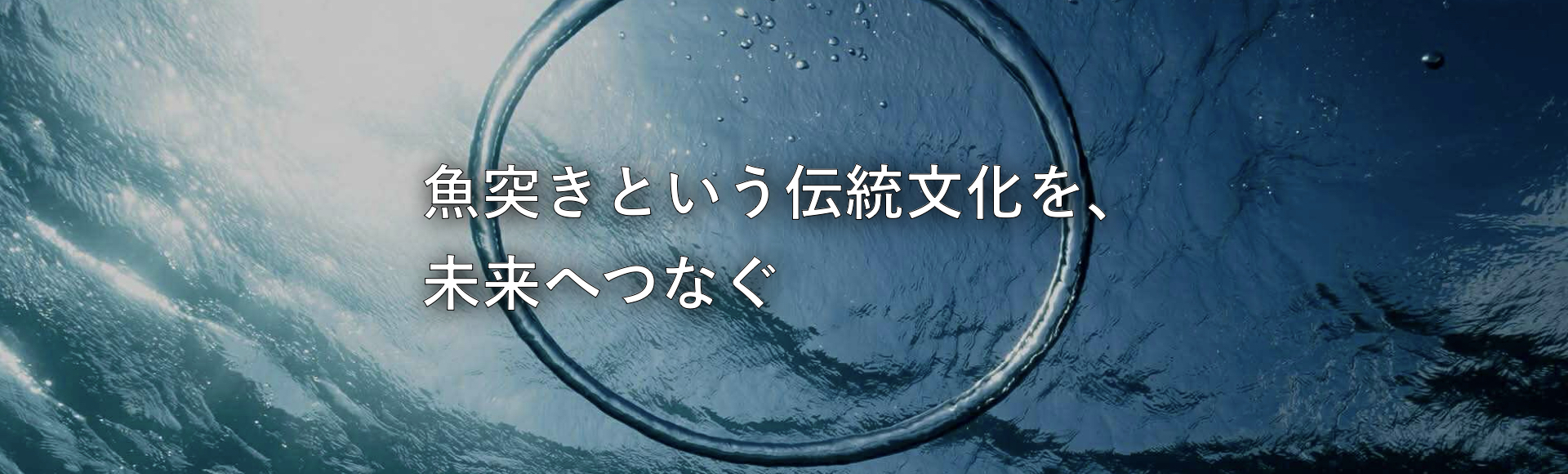「魚突きと地域の調整を図る会」のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
私たちの活動に関心を寄せてくださったことに、心より感謝申し上げます。
このサイトは、魚突きを楽しむ人々、地域で暮らす方々や漁業関係者の皆さま、そして行政に携わる方々のためのものです。
私たちは、それぞれの立場や価値観を尊重しながら、共に歩み、海や地域と調和していける関係を築くことを目指しています。
そして、魚突きをめぐる課題や可能性について互いに理解を深めるための「対話の場」となることで、
魚突きという文化を次の世代へと受け継ぎ、未来に残していきたいと願っています。
どうぞ安心してこのサイトをご覧いただき、私たちの想いや取り組みに触れていただければ幸いです。
魚突きとは
魚突きは、シュノーケルや素潜りをしながらヤスを使って魚を獲る、日本各地に古くから伝わる漁の一つです。漁業権を持つ地域では生活の一部として、また近年ではレジャーやスポーツとしても親しまれています。
特徴は以下のとおりです:
- 道具がシンプル:ヤスやゴーグル、フィンを使うだけ
- 環境への影響が比較的少ない:必要な分だけを選んで獲れる
- 伝統と文化:地域によっては昔から行われてきた漁の形
このように、魚突きは人と自然とが直に向き合う、シンプルで奥深い営みです。
だからこそ、適切な理解とルールのもとで行うことが、文化を未来へとつなぐ第一歩だと私たちは考えています。
近年の魚突きが直面している課題
魚突きは、海に潜り、自らの目で見て選んだ魚だけを獲るという、とても魅力的で文化的な価値を持つ活動です。一方で、その自由さや伝統性ゆえに、現代の社会や環境の変化の中で、新たな課題に直面する場面も増えてきました。
魚突きをよく知らない方にとっては誤解が生じやすく、また魚突きを行う側にとっても、地域や漁業との関係に慎重な配慮が求められるようになっています。そうした背景をふまえ、私たちは以下の点を特に重要な課題として認識しています。
- 安全面の課題
未経験者による無理な潜水や装備不足で事故が発生するケースがあります。 - 地域社会との摩擦
遊漁と漁業の境界があいまいになり、漁業者や地域住民との間に誤解やトラブルが生まれることがあります。 - 環境保全の観点
一部地域では資源の乱獲が懸念され、持続可能性をどう確保するかが課題となっています。 - 法的・制度的な整理不足
漁業権との関係や、遊漁としてのルール整備が地域ごとに異なり、分かりにくいのが現状です。
こうした課題は、魚突きを愛する人々だけでなく、地域に暮らす方々、漁業に携わる方々、行政の方々と共に考え、歩み寄ることで解決できるものです。
私たちは課題を単なる問題としてではなく、信頼関係を築き直すチャンスと捉え、対話の場を整えていきたいと考えています。魚突きという伝統を守りながら、地域と調和し、未来へとつなげていく道を私たちは模索しています。
私たちが大切にしていること
私たちは、魚突きを愛する人々だけでなく、地域に暮らす方々や漁業に携わる方々、そして行政の皆さまとのつながりを大切に考えています。
この活動は、どちらか一方の立場を押し通すものではなく、「みんなで海を守りながら、気持ちよく暮らしていける関係をどう築けるか」を模索する取り組みです。
そのために私たちは、次の姿勢を常に心がけています。
- 対話を重ねること
相手の立場や思いを尊重し、一方的に意見を述べるのではなく、まずは耳を傾けることから始めます。 - 調整の姿勢
魚突きをする人、地域住民、行政や漁業関係者——それぞれが抱える課題や希望のあいだに立ち、みんなが納得できる折り合いを探していきます。 - 信頼関係の構築
小さな団体だからこそ、誠実で透明な姿勢を大切に。長く安心して向き合える関係を築くことを目指しています。
私たちの活動は、まだ始まったばかりです。それでも、「まずは話してみようかな」「この団体なら安心して相談できそうだ」と思っていただけるよう、温かさと誠実さをもって活動を重ねていきます。
私たちが注目している活動
私たちは、魚突きと地域の暮らし、自然環境との調和を目指す活動を国内外から探し、学び、対話のヒントとできる取り組みを注目しています。ここでは、特に「神津島での魚突き使用ルール」と「GREEN Spearfishersのウニ間引き大作戦」という2つの事例をご紹介します。
神津島の魚突き使用ルール(東京都 神津島村)
概要:
東京・伊豆諸島の神津島では、魚突き(手銛を使った魚突き)を行う人々と地域住民、漁業関係者との間で、魚突きによる漁獲・放置魚の問題などが懸念される事態がありました。例えば、「食べることができない魚を興味本位で突いて、そのまま放置する」といった行為が報告されています。こうしたトラブルを防ぎ、魚突きを行う者が責任ある行動をとるために、神津島村では使用ルールを制定しています。 神津島村公式サイト
注目ポイント:
- 規則を設けることで、魚突きをする人がどこまで許可され、どのような行動が求められるかを明確にすることで、誤解やトラブルを未然に防ぐ仕組みを作っていること。
- 地域住民の安心感を高めることに寄与していること。自治体が主体となり、地域の実情に即したルールを設定している点。
- 魚突きを楽しむ人に対しても、「ルールを守ること」がその活動が地域社会に受け入れられる鍵であるという示唆を与えていること。
ウニ間引き大作戦 — GREEN Spearfishers(富山県 朝日町)
概要:
海藻が失われ、魚類や貝類が数を減らす“磯焼け”という現象があります。原因の一つとして、ウニが増えすぎて海藻が育てられない、あるいは回復が難しい状態が指摘されています。GREEN Spearfishersでは、地域漁協の許可を得た上で、「ウニ間引き」活動を通じて海藻が再び育つ環境を整え、海の生態系を回復させようとする活動をしています。一般の人も参加可能で、毎月の回収活動や交流会などを行っています。 Greenspearfishers
注目ポイント:
- 環境保全と地域住民の参加を両立させていること。専門家だけでなく、一般の魚突き経験者なども参加できる形式。
- 実際に“海藻が育つ場”を取り戻すことで、生きものの住処が回復し、地域の漁業や海の恵みに好影響を与える可能性があること。
- 安全条件や参加条件を明示しており、活動の透明性や参加者への配慮があること。
なぜこれらの活動に注目するのか
これらの事例は、私たちが目指す「魚突きと地域との歩み寄り」「自然環境の保全」「ルールと責任ある行動」が形になっているものです。共通して言えることは:
- 魚突きをする人たちだけでなく、地域住民・漁業者・行政など関係者すべてが安心できる環境をつくっていること。
- 活動がただ“自主的”であるだけでなく、許可・ルール・安全性などの仕組みが伴っており、責任と透明性があること。
- 環境への配慮が具体的であり、「自然を守ること」が地域の豊かさや将来につながるという視点を共有していること。
農林水産省の基本的姿勢から学ぶこと
私たちは、厚い制度的背景を持つこのような取り組みと併せて、国が 遊漁と漁業との調整 に関して示している基本姿勢にも注目しています。以下は、その通知の一部をまとめたものです。
「遊漁と漁業との調整についての基本的姿勢」(農林水産省)より抜粋:
「現在の遊漁の実態は、遊漁船業の発展、プレジャーボートの増加等、調整規則の制定当時から相当変化しており、漁業者、遊漁船業者及び遊漁者が相互に共存の努力をするとともに、資源の持続的な利用が可能となるよう資源の保存管理に努めることが必要となっている。
具体的な取り組みについては、遊漁と漁業の実態が各地で異なっているため、従来から調整規則、海区漁業調整委員会指示のほか、漁場利用協定等の当事者間の自主的な取り極め等により、各地域の遊漁と漁業の実態に即した調整が行われてきているが、今後も同様の姿勢で臨むことが適当である。なお、遊漁を含めて水産動植物の採捕規制を行う場合には、遊漁と漁業の実態を踏まえ、それぞれの規制のバランスを考慮し、遊漁に対して過度の規制とならないよう留意する必要がある。」 農林水産省
なぜこの通知が私たちにとって大切か
この通知は、私たちが目指している方向性と深く重なります。ポイントは:
- 共存の視点:漁業関係者、遊漁者、行政が互いに尊重し、対話を重ねながら、環境・資源・暮らしがバランスを保てるように取り組むこと。
- 地域実情の尊重:各地域で海の状況・漁の歴史・人々の暮らし方が違うからこそ、画一的なルールではなく、その土地に合った調整・合意が必要であること。
過度な規制の回避:遊漁者の活動を制限することで遊漁そのものの意義が損なわれないよう、規制を設けるとしても慎重に、バランスを取りながら進めるべきという配慮。
私たちが取り入れたい姿勢
このような国の姿勢を学びつつ、私たちの団体としては以下のような取り組みを目指しています:
- 地域での合意形成:漁業者・遊漁者・住民が参加する話し合いを重ね、地域ごとのルールや慣習を明らかにし、それを尊重する。
- 透明で公平なルール:遊漁の自由と責任を両立させるルールを、過度に制限するものではなく、具体的な背景や目的を示した上で作る。
規制だけでなく啓発と協力:単に禁止や制限を設けるのではなく、マナーや知識を共有し、協力・主体性を重んじる活動を促す。
私たちの活動内容
私たちは「魚突き」と「地域」がこれからも調和していけるように、
一方的に意見を押しつけるのではなく、対話を重ねながら歩み寄る姿勢を大切にしています。
そのため、次のような活動を柱として取り組んでいます。
- 魚突きに関する理解促進と情報共有
魚突きがどのような文化であり、どんな魅力や課題があるのかを、わかりやすく伝えます。 - 地域住民・漁業者・行政との話し合いの場づくり
誤解や不安を解消し、お互いの立場を尊重しながら建設的に意見を交わす場を整えます。 - 環境保全や安全に関する啓発活動
持続可能な海の利用をめざし、資源や自然を守るための取り組みを広げます。
私たちの願い
青く澄んだ海に潜り、息を整え、目の前の命をいただく——。
魚突きは、自然と人とがまっすぐに向き合う、シンプルで奥深い営みです。
けれども、その営みが続いていくためには、魚突きを楽しむ人だけでなく、
地域に暮らす人々や漁業に携わる方々、そして海を見守る行政の方々との 理解と歩み寄り が欠かせません。
私たちが願うのは、
魚突きが「危ういもの」ではなく「大切に受け継がれる文化」として根づき、
地域社会の暮らしや環境と 共に輝き続ける未来 です。
「魚突きと地域の調整を図る会」は、
その未来へとつながる 小さな架け橋 でありたいと願っています。
どうか、海を愛するすべての方々と手を取り合い、
ともに次の世代へ、この豊かなつながりを渡していけるよう活動して参ります。